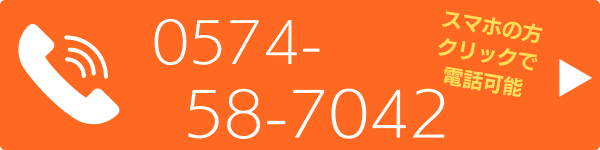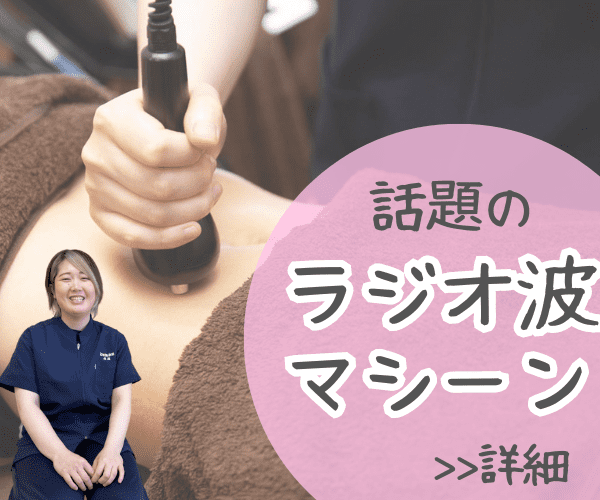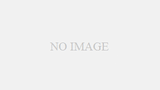足関節捻挫(ねんざ)とは?
足関節捻挫とは、足首の関節を支えている靭帯が過度に伸ばされたり、一部が損傷するケガのことを指します。特にスポーツや日常生活で足をひねった際に発生しやすく、外側の靭帯(前距腓靭帯)が最も影響を受けることが多いです。足関節捻挫の程度によっては、軽い違和感から強い痛みと腫れを伴うことがあります。
足関節捻挫は、軽度であれば自然に回復することもありますが、適切な対応を行わないと関節の不安定性が残る可能性があります。そのため、捻挫をした場合は早めに適切なケアを受けることが重要です。
足関節捻挫の主な原因
足関節捻挫は、以下のような原因で起こります。
- スポーツ中の動作:ジャンプの着地時や急な方向転換の際に足をひねることが多い。特にバスケットボールやサッカーではよく見られる。
- 不安定な地面での歩行:段差や砂利道など、不安定な場所で足を取られることがある。
- 靴の影響:クッション性のない靴やヒールの高い靴を履いていると、バランスを崩しやすい。
- 筋力やバランスの低下:足首を支える筋力が弱いと、捻挫しやすくなる。特に長期間運動をしていない人は注意が必要。
- 過去の捻挫歴:一度捻挫をしたことがあると、その後も繰り返し捻挫しやすくなる。
足関節捻挫の症状
足関節捻挫の症状は、損傷の程度によって異なります。
- 軽度(1度):軽い痛みと腫れがあり、歩行は可能だが違和感がある。日常生活には大きな影響はないが、スポーツをする際には注意が必要。
- 中程度(2度):腫れと痛みが強く、歩くのが困難になることがある。内出血が見られることもあり、関節の安定性が低下する。
- 重度(3度):靭帯が完全に損傷し、関節が不安定になる。自力での歩行が難しくなり、適切な固定とケアが必要となる。
足関節捻挫の検査と診断
医療機関では、足関節捻挫は、以下の方法で診断されます。
- 視診と触診:腫れや皮下出血、痛みの部位を確認する。
- 徒手検査(前方引き出しテスト、内反ストレステスト):足首の靭帯の安定性を評価するために行われる。
- 超音波検査(エコー):靭帯の損傷具合を確認するのに有効で、リアルタイムで状態を把握できる。
- 画像検査(X線・MRI):骨折や靭帯の完全断裂が疑われる場合に行われる。

上記は、医療機関のみで認められていることです。
足関節捻挫に対する接骨院での対応
一方、当院(接骨院)では、損傷の程度に応じて適切な対応を行います。
- RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上):炎症を抑え、回復を促進する。
- テーピングやサポーターの使用:足関節を固定し、再発を防ぐ。
- 手技による調整や電気機器を用いたケア:筋肉の緊張をほぐし、足関節の動きを整える。
- 日常生活のアドバイス:足首に負担をかけない歩き方や、回復を早めるための運動指導を行う。
足関節捻挫後の回復の流れ
足関節捻挫の回復は、以下のような段階で進みます。
- 急性期(1〜2週間):炎症を抑え、固定を行う。
- 回復期(3〜4週間):可動域を広げ、軽い負荷をかけながら足首の動きを回復
- 強化期(1〜2か月):バランス感覚を鍛え、足首の安定性を向上させる。
- 運動復帰期(2か月以降):スポーツなどの動きを段階的に再開する。
予防法の具体例
足関節捻挫を防ぐためには、次のような方法が有効です。
- ストレッチで柔軟性を向上させる(アキレス腱伸ばし、足首回し)
- バランストレーニング(片足立ちやバランスボードの使用)
- 適切なウォーミングアップを行う(ジョギングや軽いジャンプ運動)
- 足首の筋力を強化する運動を取り入れる(カーフレイズ、チューブトレーニング)
- 安定感のある靴を選ぶ
- サポーターやテーピングを活用する
放置するとどうなる?
適切な対応を受けずに放置すると、以下のようなリスクがあります。
- 関節の不安定性が残る:捻挫を繰り返しやすくなる。
- 足首の慢性的な痛み:負担がかかり続けることで慢性痛につながる。
- 歩行バランスの崩れ:足首の可動域が制限されることで、他の部位にも負担がかかる。
まとめ
- 足関節捻挫は、スポーツや日常生活で発生しやすいケガ。
- 前距腓靭帯が最も損傷しやすい。
- 診断には前方引き出しテストや超音波検査が有効。
- 接骨院では、固定やサポートを通じて回復をサポート。
- 再発防止のために、筋力トレーニングや適切な靴の選択が重要。
- 適切な対応を受けないと、慢性的な痛みや不安定性が残る可能性がある。
足首の痛みや違和感でお悩みの方は、富加接骨院までご相談ください。適切な対応で安心して日常生活に戻れるようサポートいたします。