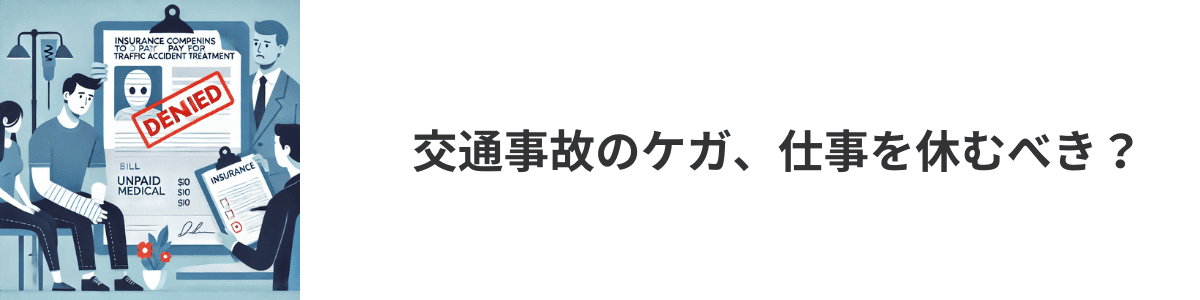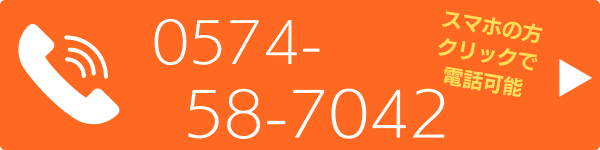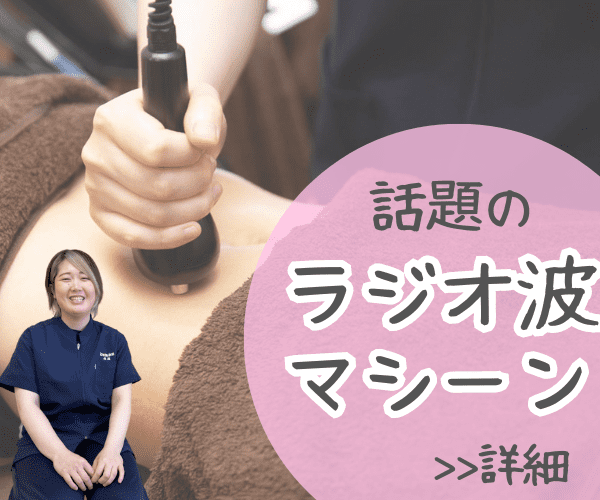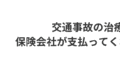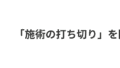交通事故でケガを負ってしまい、仕事を休むべきかどうか悩んでいませんか?
「仕事を休んだ場合、給料は補償されるの?」
「休業補償をもらうための手続きは?」
といった疑問を持つ方も多いでしょう。交通事故によるケガで仕事を休む場合、条件を満たせば「休業損害(休業補償)」を受け取ることができます。ただし、補償を受けるには適切な手続きが必要です。
この記事では、仕事を休むべきかどうかの判断基準、休業補償の仕組み、補償を受け取るための手続きについて詳しく解説します。
交通事故のケガ、仕事を休むべき?
交通事故で仕事を休むべきか?判断基準
交通事故でケガを負った場合、次のような状況なら無理をせず休むべきです。
1. 痛みが強く、業務に支障がある場合
事故後に首・腰・手足の痛みが強く、仕事に集中できない、動作に支障がある場合は、無理をせず休むことが大切です。
特に、むちうちや打撲は動かすことで悪化することもあるため、適切な施術を受けるまで無理をしないようにしましょう。
2. 医師から安静を指示された場合
整形外科や接骨院で診察を受け「安静が必要」と指示された場合は、その指示に従うことが重要です。
医師の指示を無視して仕事を続けると、症状が悪化し、結果的に長期間の施術が必要になることもあります。
3. 力仕事や長時間のデスクワークが困難な場合
仕事の内容によっては、ケガの影響で体に負担がかかることがあります。
- デスクワークの場合 → 長時間の座り仕事で腰や首に負担がかかる
- 肉体労働の場合 → 重いものを持つ作業ができない、姿勢が保てない
このような場合、無理をせず休むことを検討しましょう。
休業補償(休業損害)とは?
交通事故の影響で仕事を休んだ場合、休業補償(休業損害)を受け取れます。休業損害とは、交通事故によるケガで働けなかった期間の収入減少を補填する補償です。
休業補償の対象者
- 会社員(給与所得者)
- パート・アルバイト(収入が減った場合)
- 自営業者(確定申告をしている人)
- 主婦(主夫)(家事労働ができない場合も補償対象)
休業補償の計算方法
休業損害の金額は、次の方法で計算されます。
会社員の場合
裁判基準では『交通事故直近3か月の給与合計額 ÷ 90日 × 休業期間』で計算されます。ただし、自賠責基準では日額6,100円(上限19,000円)が適用される場合があります。
自営業者の場合
休業補償額 = 確定申告で申告した所得 ÷ 365日 × 休業日数
主婦(主夫)の場合
主婦(主夫)も「労働者」とみなされ、家事労働の価値をもとに補償が認められるケースがあります。主婦(主夫)の場合は、賃金センサスに基づく平均年収額(例:女性の場合388万1,000円)を基礎収入として計算されます。
休業補償を受け取るための手続き
休業補償を受け取るためには、適切な手続きを行うことが必要です。
1. 医師の診断書を取得する
医師の診断書に『仕事を休む必要がある』と記載してもらいましょう。診断書がなければ、保険会社は「本当に仕事を休む必要があったのか?」と疑問を持ち、補償を認めないことがあります。
2. 休業証明書を用意する
勤務先に「休業証明書」を記入してもらいます。
- 会社員・アルバイトの場合 → 会社に記入してもらう
- 自営業者の場合 → 確定申告の書類や売上台帳などを用意する
- 主婦(主夫)の場合 → 医師の診断書を提出する
3. 交通事故証明書を取得する
事故が発生したことを証明するため、警察で「交通事故証明書」を取得します。
4. 保険会社に請求する
診断書・休業証明書・交通事故証明書を揃え、加害者側の保険会社に請求します。
保険会社が対応しない場合は、自賠責保険へ被害者請求を行うこともできます。
その他の留意点
休業損害を受け取れる期間は?
休業損害は、事故発生から症状固定日までの間で、休業が必要かつ相当と認められる範囲で請求できます。
有給休暇を使った場合は?
有給休暇を使用した場合でも、本来他に利用できたはずの有給分が失われたとして、休業損害として認められることがあります。
休業損害証明書の提出頻度は?
休業損害証明書は、毎月または3か月ごとに提出することが一般的ですが、示談交渉時にまとめて請求することも可能です。
休業損害と休業給付(労災保険)は重複して受け取れる?
重複して受け取ることはできません。

休業損害と休業給付(労災保険)は重複して受け取れません。
まとめ
- 事故直後に医師の診断を受け、診断書を取得する
- 休業の記録を残す → 出勤簿や給与明細を保管
- 保険会社としっかり交渉する → 必要なら弁護士に相談
- 交通事故で痛みがある場合、無理をせず仕事を休むことが大切
- 休業補償(休業損害)は、収入減少を補填するための制度
- 会社員・自営業・主婦(主夫)など、職業に関わらず補償を受けられる場合がある
- 休業補償を受け取るためには、診断書・休業証明書・交通事故証明書を用意し、保険会社に請求する