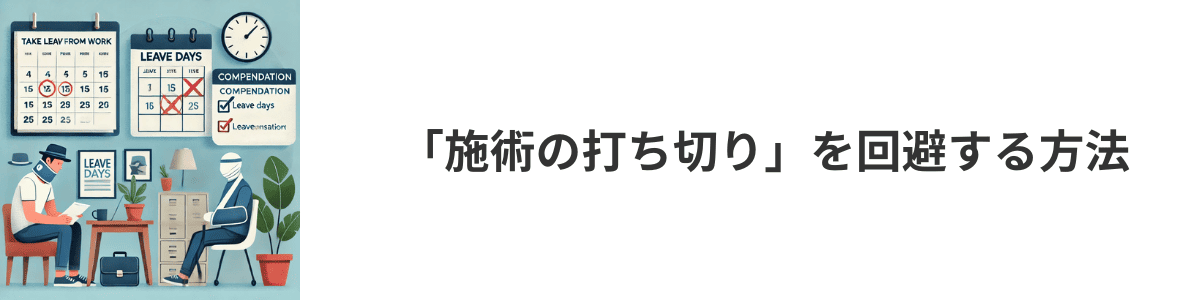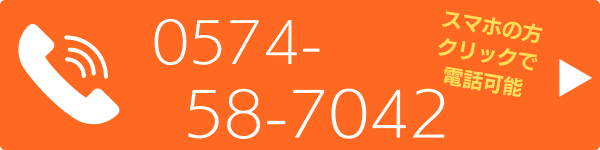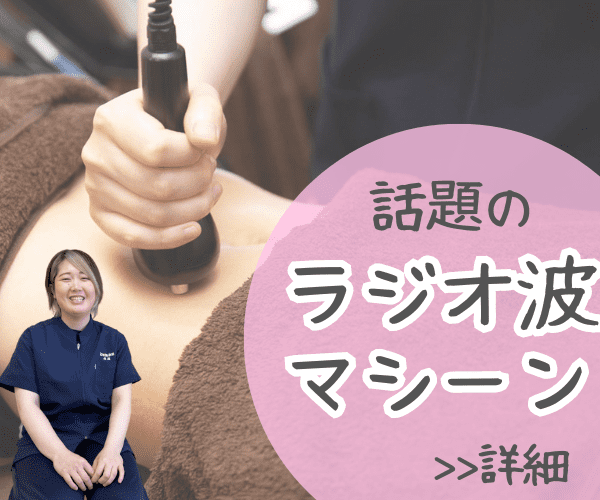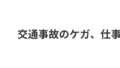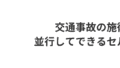交通事故でケガをした場合「どこまで通院すればいいの?」と悩む方は多いです。特に、保険会社から「そろそろ施術を終了してください」と言われた場合、本当に施術をやめていいのかと不安になりますよね。
施術を途中でやめると、痛みがぶり返したり、後遺症が残る可能性があります。また、適切な通院をしない(医師の指示に従った治療計画や通院頻度を守ること)と、慰謝料や休業補償が減額されることもあります。
この記事では、交通事故の施術をどこまで続けるべきか、保険会社による「施術打ち切り」を回避する方法について解説します。
交通事故の施術は、どこまで続けるべき?
交通事故の施術はどこまで通うべき?
交通事故のケガは個人差があり、数週間で治る軽症もあれば、半年以上かかることもあります。そのため、一概に「〇ヶ月で終了すべき」と決めることはできません。
一般的な施術期間の目安は以下の通りです。
1. 軽度のむちうち・打撲の場合
- 通院期間の目安:1〜3ヶ月
- 特徴: 事故直後は痛みを感じにくく、数日後に症状が出ることが多い
- 施術内容: 手技療法や電気施術を行い、早期回復を目指す。
2. 中程度のむちうち・捻挫・筋肉損傷の場合
- 通院期間の目安:3〜6ヶ月
- 特徴: 痛みやしびれが続き、一定期間施術を続けないと慢性化の可能性
- 施術内容: 血流を良くする施術や、筋肉・関節の動きを正常に戻す施術
3. 重度のむちうち・骨折・神経損傷の場合
- 通院期間の目安:6ヶ月以上
- 特徴: 骨折や神経の損傷がある場合、長期間の施術が必要になる
- 施術内容: 骨や関節の回復を促す施術、機能回復のための施術

症状固定(これ以上、施術しても緩和が見込めない状態)の時期によって判断されます。
保険会社が施術を打ち切ろうとする理由
多くのケースで、保険会社は3〜6ヶ月経過すると「施術を終了してください」と通告してくることがあります。その理由として、
- 長期間の通院による施術費の増加を防ぎたい
- 医学的に「施術の必要がない」と判断されたと主張する
- 通院頻度が減ると、自然回復しているとみなされる
これらが主な理由です。
「施術の打ち切り」を回避する方法
施術を打ち切られると、痛みが残っていても補償が受けられなくなることがあります。そのため、以下の方法で適切な施術を継続できるように対策をしましょう。
1. 医師の診断書・意見書を取得する
保険会社が施術費の支払いを打ち切る理由の一つが「医学的に施術の必要がない」と判断されることです。そのため、担当医師に「まだ施術が必要」と記載された診断書や意見書を発行してもらうことが重要です。
2. 定期的に整形外科で診察を受ける
接骨院での施術を続ける場合も、定期的に整形外科で診察を受けることが大切です。なぜなら、保険会社は医師の診察結果を重視するため「まだ症状が良くなっていない」と証明することができるからです。
3. 通院頻度を一定に保つ
- 通院の間隔が空きすぎると「施術の必要がない」と判断されることがあります。
- 最初の2〜3ヶ月はできるだけ頻繁に通院し、その後は症状に応じて徐々に回数を減らすのが理想的です。
4. 体調が改善しない場合は、適切に主張する
保険会社から「施術の打ち切り」を言われても、症状が改善しない場合は、その旨をしっかり主張しましょう!
- 「痛みがまだ続いている」
- 「日常生活に支障がある」
- 「医師の診断では、引き続き施術が必要とされている」
このように具体的な症状を伝えることで、施術の必要性を証明しやすくなります。
5. 弁護士に相談する
保険会社との交渉が難しい場合は、弁護士に相談するのも有効です。
特に、任意保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、無料で弁護士を利用できるため、施術費の支払い交渉をサポートしてもらえます。
まとめ
- 交通事故の施術期間は、軽度なら1〜3ヶ月、中程度なら3〜6ヶ月、重度なら6ヶ月以上かかることがある
- 保険会社は3〜6ヶ月で施術費の打ち切りを求めることが多い。
- 診断書や通院記録を管理し、適切な通院頻度を維持することで施術の必要性を証明できる。
- 症状が残っている場合は、保険会社に適切に主張し、必要なら弁護士への相談も検討する。