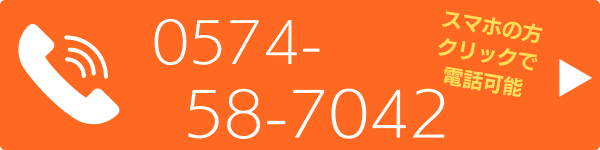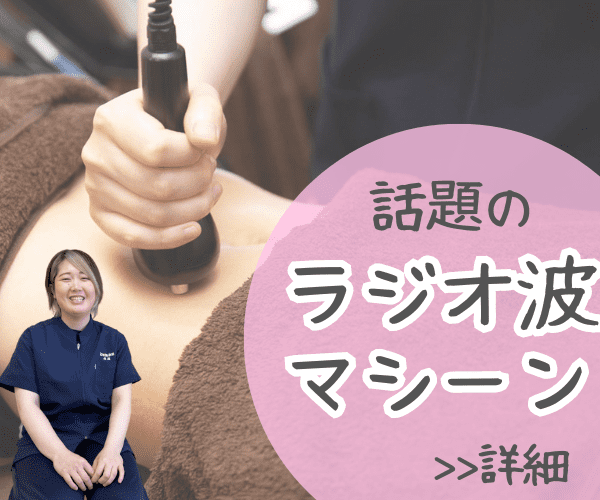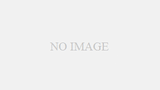側副靭帯損傷とは?
側副靭帯損傷とは、関節を安定させる側副靭帯(内側または外側)が伸びたり、部分的に切れたりするケガのことです。特に指や膝、肘などの関節で起こりやすく、スポーツや転倒などで発生することが多いです。
損傷の程度によっては、軽度の捻挫のような状態から、手術が必要となる重度の損傷まで幅広く分かれます。適切な処置をしないと関節の安定性が失われ、痛みや動きの制限が長引くことがあります。
側副靭帯損傷の主な原因
側副靭帯損傷は、関節に外から強い力が加わることで発生します。主な原因には以下のようなものがあります。
- スポーツ中のケガ:バスケットボールやバレーボールで指を突いたとき、サッカーや柔道で膝に負荷がかかったとき。特に指や膝は靭帯が弱いため、急な動きや衝撃によって損傷しやすくなります。
- 転倒や事故:手や膝をついたときに強い衝撃が加わることで、靭帯に過剰な負荷がかかり損傷する。階段での転倒や交通事故も原因の一つ。
- 急激な動作や負荷:関節に強いひねりが加わる動きや、無理な負荷がかかった際に損傷が発生しやすい。特にウエイトトレーニングや急な方向転換を伴うスポーツでは注意が必要。
- 加齢や筋力低下:年齢を重ねると靭帯が弱くなり、軽い負荷でも損傷するリスクが高まる。筋力が低下すると関節を支える力が弱まり、損傷のリスクが増す。
RICE処置(応急処置の基本)
側副靭帯損傷の急性期には、適切な応急処置を行うことが回復を早めるポイントです。基本的な処置として、RICE処置(Rest, Ice, Compression, Elevation)が推奨されます。
- Rest(安静):ケガをした関節を動かさず、負担をかけないようにする。無理に動かすと損傷が悪化する可能性がある。
- Ice(冷却):氷や冷却パックを使い、15〜20分程度冷やす。炎症を抑え、腫れや痛みを軽減する。
- Compression(圧迫):テーピングや包帯を使い、軽く圧迫することで腫れを防ぐ。ただし、強く締めすぎると血流を妨げるため注意が必要。
- Elevation(挙上):損傷した部位を心臓より高い位置に持ち上げ、血流を調整し腫れを抑える。
緩和期の段階
側副靭帯損傷の緩和行為は、段階的に進めることが重要です。
1. 急性期(1〜2週間)
- RICE処置を徹底し、安静を保つ
- 痛みが落ち着いてきたら、軽いストレッチを開始
2. 回復期(3〜6週間)
- 軽い負荷をかけながら関節の可動域を広げる運動を行う
- 軽い筋力トレーニングを開始(例:足や指のグーパー運動など)
3. 強化期(7週間〜3か月)
- 日常生活動作を徐々に増やし、関節の安定性を高めるトレーニング
- 片足立ちやスクワットなど、バランスを意識した運動を取り入れる
4. スポーツ復帰期(3か月〜6か月)
- 徐々にスポーツ動作を取り入れ、無理のない範囲で運動を再開
- 専門家の指導のもと、適切なストレッチとトレーニングを続ける
スポーツ復帰の目安
一般的なスポーツ復帰の目安は以下の通りです。
- 保存療法の場合:2〜4か月程度で軽い運動が可能
- 手術療法の場合:半年〜1年程度で本格的なスポーツ復帰が可能
個人の回復速度には差があるため、専門家と相談しながら無理のない復帰を心がけましょう。
側副靭帯損傷の予防法
側副靭帯損傷を防ぐためには、日頃からのケアが重要です。
- 関節を強化する筋力トレーニング:太ももや足首、指の筋力を鍛え、関節を安定させる。
- 適切なウォーミングアップとクールダウン:運動前後にしっかりストレッチを行う。
- 正しいフォームを意識する:スポーツ時の姿勢や動きを見直し、過剰な負担を避ける。
- 適切なサポーターやテーピングを活用する:関節の負担を軽減し、怪我を防ぐ。
専門医への相談
もし以下のような症状がある場合は、整形外科などの専門医に相談することをおすすめします。
- 痛みが長引き、回復の兆しが見られない
- 関節が不安定で、力が入りにくい
- 夜間に痛みが増し、睡眠の妨げになる
- しびれや感覚異常がある
まとめ
- 側副靭帯損傷は関節の安定を保つ靭帯が損傷するケガ
- 急性期にはRICE処置を徹底し、適切な固定と安静が重要
- 接骨院では固定や施術を通じて回復をサポート
- スポーツ復帰には数か月単位の回復期間が必要
- 予防のために筋力トレーニングやストレッチを習慣化する
側副靭帯損傷による痛みや違和感でお悩みの方は、富加接骨院までご相談ください。適切な施術で早期回復をサポートします。